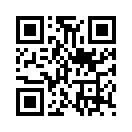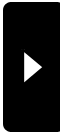2012年01月31日
テンノウメ 方言ではテンバイ
テンノウメ テンバイ
http://stewartia.net/engei/tree/Bara_Ka/Osteomeles.html
隆起サンゴ礁上に生える植物で、花は梅の花に似ています。
昔は盆栽用に乱獲されたために採取が禁止されています。
沖縄ではテンノウメの盆栽展が開催されているようです。
サンショウの木と似ていますが、葉の照りがあります。
2012年01月31日
ハート型の実を漬けるハリツルマサキ
ハート形の実をつけるハリツルマサキ
http://tenant.depart.livedoor.com/t/musashinokadan/item5656250.html
変異種のようです。
琉球石灰岩場に生えるつる性植物です。
2012年01月31日
黒貫字 水神祭を行っているそうです。
黒貫集落紹介
http://www.town.china.lg.jp/modules/soumu/index.php?content_id=41
11月23日に水神祭を行なっているようです。
知名町HPより
タグ :黒貫字紹介 HPより
2012年01月30日
田芋の収穫体験&ランチ 沖縄
田芋の収穫体験
http://tidana.ti-da.net/e3711782.html
沖永良部島では竿津・赤嶺で栽培されています。
各湧水の場所でもよく見かけます。
水が流れる場所じゃないと堅い芯が入るそうです。
昔は冬場の作物でしたが、近年沖縄から導入された品種は1年中栽培できるようです。
田芋の茎料理ムジ炒めは大城ゆうゆう市横の料理屋松竹で食べることができます。
大城でも田芋が栽培されています。
タグ :田芋の収穫体験
2012年01月30日
アオバナハイノキ

アオバナハイノキ
沖永良部島が北限種です。
3月ごろに花を咲かせます。大山植物園に数本木があります。
北限種他にはヤエヤマハマナツメ、ボウコツルマメ、ハスノハギリなどがあります。
2012年01月29日
2012年01月29日
2012年01月29日
クレソン繁茂
クレソン
いろんな場所で見かけます。
外来種
綺麗な水の場所では食用として利用されます。
大城ゆうゆう市で販売されており、とうぐらがよく利用しているようです。
水田地帯では繁殖力が強いために雑草扱いされています。
タグ :クレソン
2012年01月28日
2012年01月28日
2012年01月28日
寒緋桜 カンヒサクラ
寒緋桜(カンヒサクラ) 彼岸桜とヒカンサクラ(緋寒桜)間違えやすいために、寒緋桜に変更しようとのことでカンヒサクラが現在は正式名称です。
沖縄では新聞記事など寒緋桜で統一されていますが、奄美はまだのようです。新聞記事など名称に注意して見ると面白いですよ。
2012年01月27日
2012年01月27日
2012年01月26日
奄美群島の在来作物 栽培作物
奄美群島の在来作物
http://www.amami.or.jp/kouiki/seibutsusigen/vegit_syurui_list.html
奄美群島生物資源より
タグ :奄美群島の在来作物
2012年01月26日
琉球石灰岩の植物
琉球石灰岩の植物
http://www.geocities.jp/michi_kba/matuda/kouryuson-ni1.html
沖永良部島の海岸線の植物は観光客には目新しい植物で、エコガイドとしての目玉になります。
2012年01月25日
龍郷町の環境教育シンポジウムについて
南海日日新聞より
奄美群島の自然を生かした環境教育の方向性を考える環境教育シンポジウム(龍郷町教育委員会主催)が3日夜、龍郷町であった。国や地元の研究者ら約60人が参加。奄美の世界自然遺産登録も視野に、次代を担う子どもの探究心や創造力を育む手法として、身近な自然を教材に地域で活動して課題を地球規模で考えるアースシステム教育が提案された。行政と民間の連携拡充を求める意見も出た。
同町教委は「持続発展教育」(ESD)の取り組みで、地元の専門家を講師に奄美の豊かな自然や文化を科学的な視点で体験学習し、知識と探究心や感性を磨く「子ども博物学士講座」などの環境教育を推進しており、シンポジウムもその一環で開催。活動を指導する国立教育政策研究所・教育課程研究センターの五島政一総括研究官がアースシステム教育を提案した。
五島総括研究官は、科学的探究心を深めるアースシステム教育の指導方法について①地域の自然で課題を発見(野外学習)し、課題をグループで協力して探求する学習を展開する②課題に関する資料や情報をインターネットで世界から収集したり、コンピューターを利用したりして学習する―などを挙げた。
また、アースシステム教育の一つに環境教育を挙げ、「科学は、人間が生きる上で大事な感性と感動を育む。自然の美しさと不思議さと畏敬の念、学問の楽しさを体感させ、奄美に愛着と誇りを持つ子どもを育てよう」などと呼び掛けた。
シンポジウムは「持続可能社会をめざした奄美の10年を考える夕べin知の噴火口 龍郷」がテーマ。奄美の動植物を研究する地元各種団体の代表が希少種や進化を遂げた固有種も示しながら「生物の進化の理解は心の教育につながる」などと意見発表、世界的価値を持つ生物の多様性を次代へ引き継ぐために「行政と民間の連携を拡充した環境教育や外来種対策の推進が必要」との声もあった。
タグ :龍郷町環境シンポジウム
2012年01月25日
セイロンベンケイ
セイロンベンケイ
http://www.nippon-shinyaku.co.jp/herb/db/arekore/41_50/bryophyllum_pinnatum.html
今花を咲かせています。
薬草としての効果もあるようです。
南アフリカ原産
葉から根を出し成長する逞しい植物です。
タグ :セイロンベンケイ
2012年01月24日
イソアワモチ
イソアワモチ
食べれます。
味は磯の風味が満載で少し苦味があります。
貝を持たない巻貝の仲間です。
梅雨時期に多く発生します。
珍味ですね。
ウミウシの仲間としてダイバーに人気の食材です。
タグ :イソアワモチ
2012年01月24日
2012年01月23日
ヤブニッケイ
ヤブニッケイ
樹の名前を書いた名札があると便利ですね。
大山植物園も昔は其々の樹に名札が付けられていました。
明日はエコガイド協議会の会合です。
大山植物園の再生を提案する予定です。
地元にあるものの価値を理解しPRすることが密着型の観光の基本です。